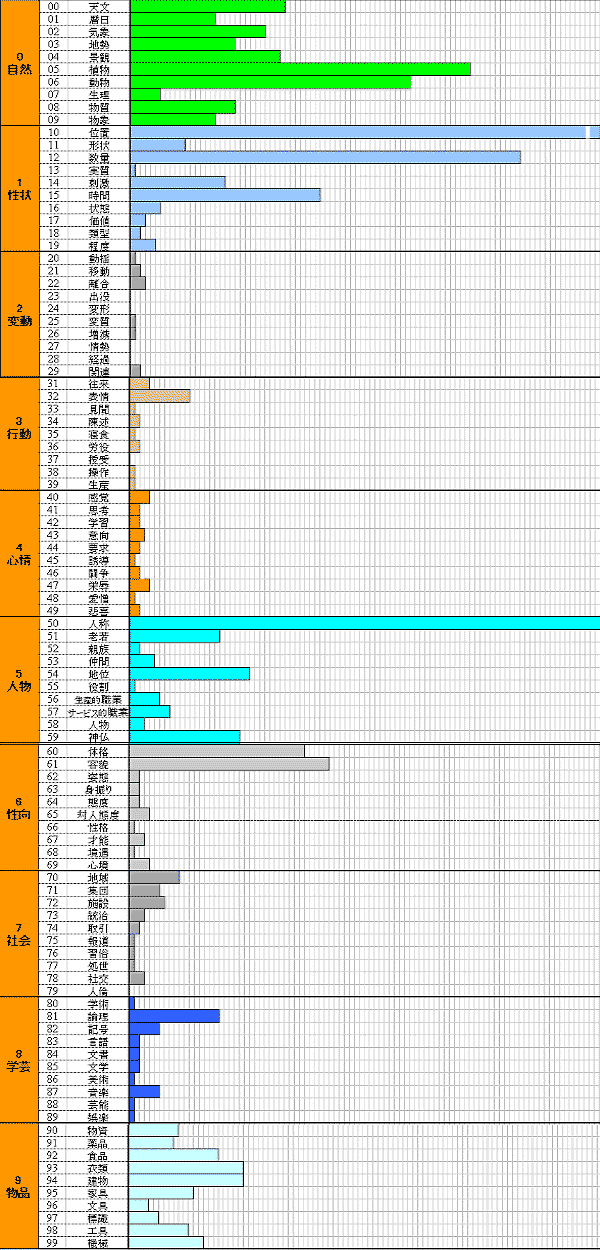
| 分類/作品名 | 序 | どんぐり | 狼森と | 注文の | 烏の北斗 | 水仙月 | 山男の | 月夜の | かしは | 鹿踊り | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 自 然 | 00 | 天文 | 2 | 7 | 12 | 0 | 35 | 33 | 7 | 12 | 34 | 13 | 155 |
| 01 | 暦日 | 4 | 14 | 22 | 2 | 8 | 19 | 0 | 3 | 8 | 3 | 83 | |
| 02 | 気象 | 3 | 5 | 8 | 3 | 17 | 51 | 8 | 8 | 18 | 11 | 132 | |
| 03 | 地勢 | 2 | 13 | 15 | 5 | 7 | 29 | 5 | 1 | 7 | 18 | 102 | |
| 04 | 景観 | 5 | 15 | 71 | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 19 | 8 | 144 | |
| 05 | 植物 | 0 | 69 | 52 | 14 | 22 | 24 | 10 | 1 | 74 | 74 | 340 | |
| 06 | 動物 | 0 | 52 | 15 | 17 | 62 | 8 | 28 | 3 | 35 | 61 | 281 | |
| 07 | 生理 | 0 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 31 | |
| 08 | 物質 | 1 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 18 | 5 | 11 | 12 | 102 | |
| 09 | 物象 | 2 | 4 | 13 | 2 | 13 | 17 | 5 | 12 | 12 | 5 | 85 | |
| 19 | 195 | 219 | 57 | 192 | 201 | 92 | 50 | 218 | 212 | 1455 | |||
| 1 性 状 | 10 | 位置 | 7 | 77 | 100 | 95 | 78 | 104 | 81 | 53 | 74 | 108 | 777 |
| 11 | 形状 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 16 | 54 | |
| 12 | 数量 | 3 | 24 | 83 | 49 | 34 | 27 | 31 | 33 | 44 | 60 | 388 | |
| 13 | 実質 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 刺激 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 17 | 7 | 3 | 26 | 15 | 92 | |
| 15 | 時間 | 2 | 11 | 24 | 12 | 24 | 13 | 21 | 15 | 39 | 27 | 188 | |
| 16 | 状態 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 28 | |
| 17 | 価値 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 14 | |
| 18 | 類型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 19 | 程度 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1 | 23 | |
| 17 | 124 | 218 | 172 | 153 | 170 | 153 | 118 | 214 | 236 | 1575 | |||
| 2 変 動 | 20 | 動揺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 移動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
| 22 | 離合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 14 | |
| 23 | 出没 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 変形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 変質 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | 情勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 経過 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 関連 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | 41 | |||
| 3 行 動 | 30 | 動作 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 31 | 往来 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 16 | |
| 32 | 表情 | 0 | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 10 | 3 | 53 | |
| 33 | 見聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 陳述 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 35 | 寝食 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 労役 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 37 | 授受 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 操作 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 39 | 生産 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 8 | 13 | 11 | 17 | 11 | 14 | 9 | 15 | 7 | 105 | |||
| 4 心 情 | 40 | 感覚 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 20 |
| 41 | 思考 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 42 | 学習 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 43 | 意向 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 44 | 要求 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 45 | 誘導 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 46 | 闘争 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 47 | 栄辱 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | |
| 48 | 愛憎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 49 | 悲喜 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 2 | 12 | 9 | 22 | 14 | 2 | 11 | 4 | 24 | 9 | 109 | |||
| 5 人 物 | 50 | 人称 | 11 | 66 | 30 | 36 | 37 | 22 | 102 | 33 | 90 | 43 | 470 |
| 51 | 老若 | 0 | 9 | 26 | 0 | 4 | 23 | 1 | 17 | 2 | 3 | 85 | |
| 52 | 親族 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 53 | 仲間 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | |
| 54 | 地位 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 1 | 0 | 16 | 27 | 5 | 117 | |
| 55 | 役割 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 56 | 生産的職業 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | |
| 57 | サービス的職業 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 40 | |
| 58 | 人物 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
| 59 | 神仏 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 39 | 0 | 1 | 0 | 108 | |
| 11 | 96 | 72 | 57 | 114 | 111 | 149 | 75 | 161 | 52 | 898 | |||
| 6 性 向 | 60 | 体格 | 0 | 14 | 11 | 10 | 19 | 10 | 32 | 22 | 31 | 21 | 170 |
| 61 | 容貌 | 0 | 31 | 12 | 19 | 13 | 37 | 20 | 11 | 22 | 35 | 200 | |
| 62 | 姿態 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 63 | 身振り | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 64 | 態度 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 65 | 対人態度 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | |
| 66 | 性格 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 67 | 才能 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | |
| 68 | 境遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 69 | 心境 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 19 | |
| 0 | 54 | 31 | 32 | 41 | 52 | 62 | 41 | 81 | 64 | 458 | |||
| 7 社 会 | 70 | 地域 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 13 | 11 | 3 | 2 | 48 |
| 71 | 集団 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 28 | |
| 72 | 施設 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
| 73 | 統治 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| 74 | 取引 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 75 | 報道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 76 | 習俗 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 77 | 処世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 78 | 社交 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 79 | 人倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 22 | 1 | 29 | 22 | 9 | 23 | 28 | 8 | 5 | 148 | |||
| 8 学 芸 | 80 | 学術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 | 論理 | 9 | 5 | 9 | 18 | 12 | 2 | 10 | 10 | 8 | 3 | 86 | |
| 82 | 記号 | 0 | 11 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 31 | |
| 83 | 言語 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | |
| 84 | 文書 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 85 | 文学 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 86 | 美術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 87 | 音楽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 1 | 32 | |
| 88 | 芸能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 89 | 娯楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 30 | 18 | 30 | 12 | 4 | 12 | 22 | 40 | 12 | 191 | |||
| 9 物 品 | 90 | 物資 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2 | 4 | 10 | 4 | 9 | 2 | 51 |
| 91 | 薬品 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 47 | |
| 92 | 食品 | 3 | 7 | 15 | 16 | 3 | 9 | 10 | 0 | 12 | 16 | 91 | |
| 93 | 衣類 | 5 | 17 | 3 | 16 | 1 | 16 | 10 | 11 | 17 | 17 | 113 | |
| 94 | 建物 | 0 | 6 | 13 | 51 | 4 | 3 | 2 | 30 | 1 | 1 | 111 | |
| 95 | 家具 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 2 | 22 | 7 | 6 | 1 | 64 | |
| 96 | 文具 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | |
| 97 | 標識 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 32 | |
| 98 | 工具 | 0 | 7 | 13 | 8 | 2 | 7 | 1 | 18 | 4 | 2 | 62 | |
| 99 | 機械 | 0 | 22 | 3 | 8 | 22 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 73 | |
| 8 | 68 | 58 | 147 | 35 | 49 | 88 | 89 | 81 | 43 | 666 | |||
| 69 | 610 | 639 | 557 | 609 | 614 | 615 | 444 | 843 | 646 | 5646 |
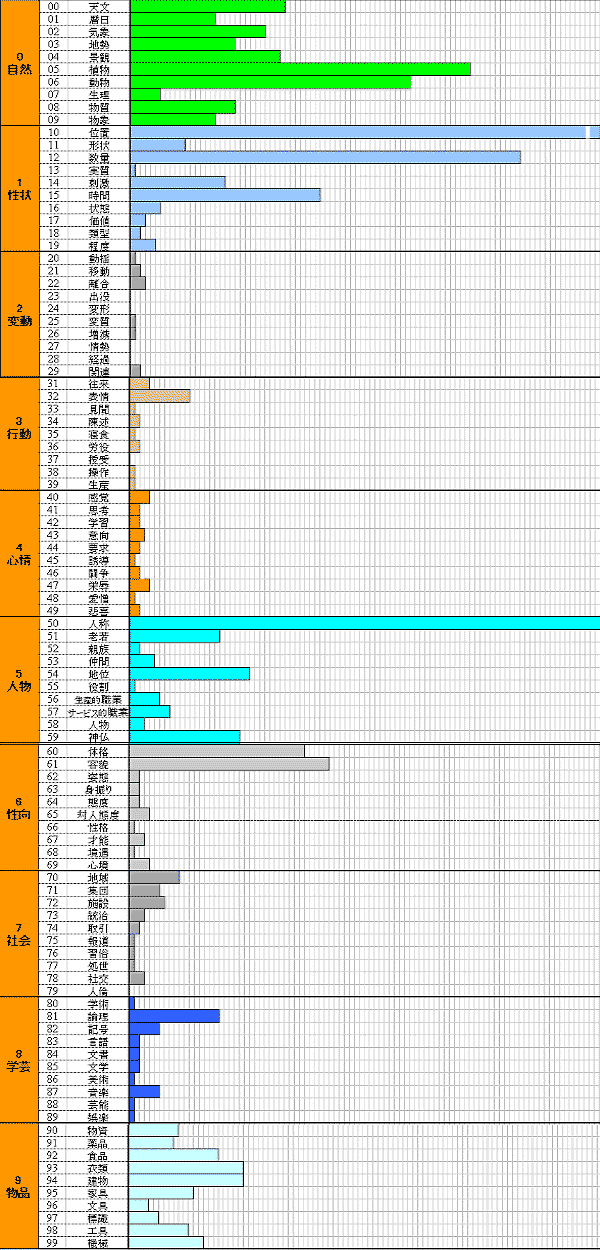
| 【狼森と笊森、盗森】 | するとある年の秋、水のやうにつめたいすきとほる風が、柏の枯れ葉をさらさら鳴らし、岩手山の銀の冠には、雲の影がくつきり黒くうつつてゐる日でした。 |
| 【烏の北斗七星】 | つめたいいぢの悪い雲が、地べたにすれすれに垂れましたので、野はらは雪のあかりだか、日のあかりだか判らないやうになりました。 |
| 【烏の北斗七星】 | 烏の義勇艦隊は、その雲に圧しつけられて、しかたなくちよつとの間、亜鉛の板をひろげたやうな雪の田圃のうへに横にならんで仮泊といふことをやりました。 |
| 【烏の北斗七星】 | 雲がやつと少し上の方にのぼりましたので、とにかく烏の飛ぶくらゐのすき間ができました。 |
| 【烏の北斗七星】 | そのときはもうまつ先の烏の大尉は、四へんほど空で螺旋を巻いてしまつて雲の鼻つ端まで行つて、そこからこんどはまつ直ぐに向ふの杜に進むところでした。 |
| 【烏の北斗七星】 | 雲はうす黒く、ただ西の山のうへだけ濁つた水色の天の淵がのぞいて底光りしてゐます。 |
| 【烏の北斗七星】 | 雲がすつかり消えて、新しく灼かれた鋼の空に、つめたいつめたい光がみなぎり、小さな星がいくつか聯合して爆発をやり、水車の心棒がキイキイ云ひます。 |
| 【水仙月の四日】 | 猫のやうな耳をもち、ぼやぼやした灰いろの髪をした雪婆んごは、西の山脈の、ちぢれたぎらぎらの雲を越えて、遠くへでかけてゐたのです。 |
| 【水仙月の四日】 | こいつらは人の眼には見えないのですが、一ぺん風に狂ひ出すと、台地のはづれの雪の上から、すぐぼやぼやの雪雲をふんで、空をかけまはりもするのです。 |
| 【水仙月の四日】 | すると、雲もなく研きあげられたやうな群青の空から、まつ白な雪が、さぎの毛のやうに、いちめんに落ちてきました。 |
| 【水仙月の四日】 | 雪だか雲だかもわからないのです。 |
| 【水仙月の四日】 | どんどんかける黒雲の間から、その尖つた耳と、ぎらぎら光る黄金の眼も見えます。 |
| 【水仙月の四日】 | 狼どもが気ちがひのやうにかけめぐり、黒い足は雪雲の間からちらちらしました。 |
| 【水仙月の四日】 | そして、風と雪と、ぼさぼさの灰のやうな雲のなかで、ほんたうに日は暮れ雪は夜ぢう降つて降つて降つたのです。 |
| 【山男の四月】 | 山男がこんなことをぼんやり考へてゐますと、その澄み切つた碧いそらをふわふわうるんだ雲が、あてもなく東の方へ飛んで行きました。 |
| 【山男の四月】 | (ぜんたい雲といふものは、風のぐあひで、行つたり来たりぽかつと無くなつてみたり、俄かにまたでてきたりするもんだ。そこで雲助とかういふのだ。) |
| 【山男の四月】 | 雲はひかつてそらをかけ、かれ草はかんばしくあたたかです。 |
| 【かしはばやしの夜】 | 清作はすつかりどぎまぎしましたが、ちやうど夕がたでおなかが空いて、雲が団子のやうに見えてゐましたからあわてて、「えつ、今晩は。よいお晩でございます。えつ。お空はこれから銀のきな粉でまぶされます。ごめんなさい。」と言ひました。 |
| 【かしはばやしの夜】 | 林を出てから空を見ますと、さつきまでお月さまのあつたあたりはやつとぼんやりあかるくて、そこを黒い犬のやうな形の雲がかけて行き、林のずうつと向ふの沼森のあたりから、「赤いしやつぽのカンカラカンのカアン。」と画かきが力いつぱい叫んでゐる声がかすかにきこえまし |
| 【月夜のでんしんばしら】 | そしてうろこ雲が空いつぱいでした。 |
| 【月夜のでんしんばしら】 | うろこぐもはみんな、もう月のひかりがはらわたの底までもしみとほつてよろよろするといふふうでした。 |
| 【月夜のでんしんばしら】 | その雲のすきまからときどき冷たい星がぴつかりぴつかり顔をだしました。 |
| 【月夜のでんしんばしら】 | 二人の影ももうずうつと遠くの緑青いろの林の方へ行つてしまひ、月がうろこ雲からぱつと出て、あたりはにはかに明るくなりました。 |
| 【月夜のでんしんばしら】 | ぢいさんはしばらく月や雲の工合をながめてゐましたが、あまり恭一が青くなつてがたがたふるえてゐるのを見て、気の毒になつたらしく、少ししづかに斯う云ひました。 |
| 【月夜のでんしんばしら】 | でんしんばしらはしづかにうなり、シグナルはがたりとあがつて、月はまたうろこ雲のなかにはいりました。 |
| 【鹿踊りのはじまり】 | そのとき西のぎらぎらのちぢれた雲のあひだから、夕陽は赤くななめに苔の野原に注ぎ、すすきはみんな白い火のやうにゆれて光りました。 |
| 【かしはばやしの夜】 | 「雨はざあざあざつざざざざざあ/風はどうどうどつどどどどどう/あられぱらぱらぱらぱらつたたあ/雨はざあざあざつざざざざざあ」 |
| 【かしはばやしの夜】 | 「こざる、こざる、/おまへのこしかけぬれてるぞ、/霧、ぽつしやんぽつしやんぽつしやん、/おまへのこしかけくされるぞ。」 |
| 【かしはばやしの夜】 | 「あつだめだ、霧が落ちてきた。」とふくらふの副官が高く叫びました。 |
| 【かしはばやしの夜】 | なるほど月はもう青白い霧にかくされてしまつてぼおつと円く見えるだけ、その霧はまるで矢のやうに林の中に降りてくるのでした。 |
| 【かしはばやしの夜】 | 冷たい霧がさつと清作の顔にかかりました。 |
| 【かしはばやしの夜】 | 霧の中を飛び術のまだできてゐないふくらふの、ばたばた遁げて行く音がしました。 |
 |