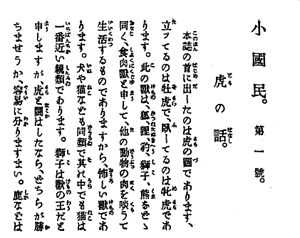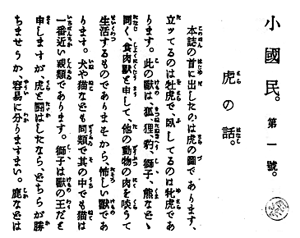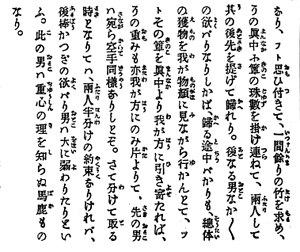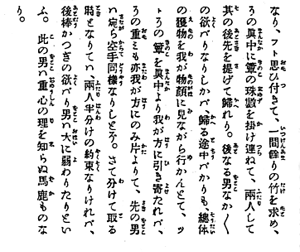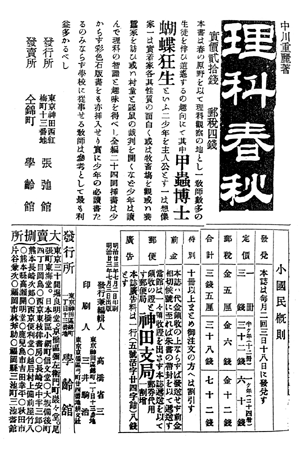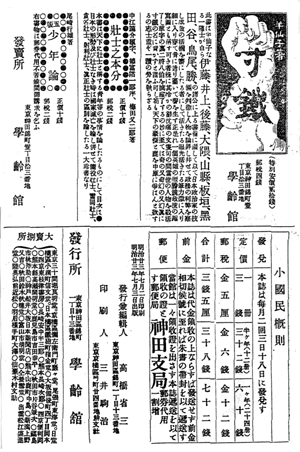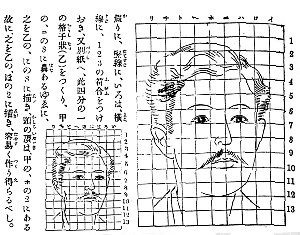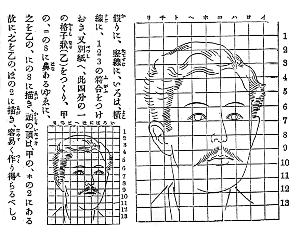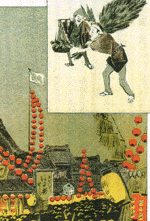「小国民」誌の異版
「国際児童文学館紀要」第16号(2001.3.31 大阪国際児童文学館)に発表
=目次=
(1)はじめに
(2)本文の組版について
(3)図版について
(4)口絵について
(5)おわりに
(1)はじめに
雑誌「小国民」は明治期を代表する児童雑誌の一つである。
創刊当初の発行人は高橋省三であった。この人物の経歴はよく分かっていないが、木村小舟の『少年文学史 明治篇』上巻(1942年7月10日 童話春秋社)によると、岐阜県の出身で一時期は少年園(「少年園」誌の発行元)の営業部に勤務したことがあったらしい。また、この雑誌のごく初期の号から、石井研堂が実質上の主筆(編集長)を務めていたようである。最盛期は日清戦争のころという。しかし、第7年第1号(1895年1月1日付)に掲載した記事「海軍の信号」が軍機に触れるとして告発された。記事の内容が手旗信号を紹介していたためである。これについては、裁判中に戦争が終結し法令自体が廃止されたので事なきを得たものの、さらに追い打ちをかけるように、この年の第7年第18号(1895年9月15日付)に至って発行・発売禁止の処分を受けた。その理由は「嗚呼露国」と題する記事がいわゆる三国干渉に論及して当局の怒りを招いたためと言われる。この処分を機に、誌名を「少国民」に変更して改題第1号(1895年11月10日付)を刊行。翌年には高橋省三が経営権を北隆館に譲り渡している。加えて1899年に石井研堂が去ってからは特に誌勢が振るわず、第14年第28号(1902年12月1日付)をもって廃刊となった。
かつて、わたしは『国際児童文学館紀要』第2号(1986年3月31日)と第3号(同年12月31日)で、この雑誌の総目次(細目)を共同で執筆したことがあった。そのおりには異版の存在に気づかないまま終始したが、その後、復刻版「小国民」(上笙一郎・上田信道編 1998〜99 不二出版)の編集・刊行に携わる機会に恵まれた。復刻版を刊行するためには、可能な限りの複本を集めた上でそれらを校合し、底本を決定する。こうした過程を通じて、初めてこの雑誌に多くの異版が存在していることを確認し得た次第である。
異版の存在については、復刻版の「解説・解題」にも書いておいた。しかし、こうした性格の論考では、異版についてはごく簡単に論及するだけに留めておかざるを得なかった。そこで、本稿では「小国民」の復刻の対象となった号について、復刻で底本とした版(以下、単に「底本」とする)と復刻版で採用しなかった版(以下、単に「異版」とする)を校合して詳解する。これを通じて、草創期の児童雑誌における再版の刊行をめぐる諸問題、挿画や図版・口絵をめぐる諸問題について考究したい。同時に、希有の出版文化人であった石井研堂の業績の一端を浮き彫りにすることができるであろう。なお、復刻版の対象となった「小国民」は、創刊号(1889年7月10日付)から「少国民」に改題後の改題第3号(1895年12月15日付)までについてであり、本稿における考察の対象も同様である。
(2)本文の組版について
「小国民」は同時代に刊行されていた「少年園」や「日本之少年」に比べると、低い年齢層の読者に焦点をあてた雑誌であった。創刊号の緒言(事実上の創刊の辞)は「拝啓、我が幼き国民、第二の日本国民たる、幼年諸君足下」云々という呼びかけで始まっている。ここにいう幼年とは、おおむね小学生(当時は4年制)を指すものと考えて良い。記事の文体についても言文一致体を基本にし、文語体を採用する場合でもなるべく平易な表現になるように配慮されている。これまで適当な総合雑誌を有していなかった年齢層の子どもが、初めてその機会を手にすることができたのである。
発行部数を窺わせる記事としては、第1年第4号(1889年10月10日付)に「今や巳(ママ)に八千余部を刷り出すほどの勢に相成候に付」云々とある。また、第3年第1号(1891年1月3日付)の「館告」には「小国民は、すでに、小学雑誌の王位を棄て日本諸雑誌の王位を占むるに至れり」云々と誇らしげに宣言され、第3年第2号(1891年1月18日付)には「今は三万に埀とする」云々、第4年第18号(1892年9月18日付)には「十万余部」という記述がある。宣伝のため誇張のあることは割り引いても、当時としては驚くべき発行部数である。研堂が『「小国民」綜覧』(1941年10月21日)で回想するところによれば、日清戦争中が本誌の最盛期であり、この頃は1万5千部発行されたという。おそらく、このあたりが平均的な実売部数であろうか。
このように売れ行きが好調であったため、店頭で売り切れて版元でも在庫切れになる状態が恒常的に続いていた。例えば、第2年第22号(1890年11月3日付)の「館告」によると「本誌、十八、十九、二十の三号は、売切れにて、御注文に応じがたかりしが、何れも、再版出来上りたれば」云々とある。当初、これほどの売り上げをあげることは、版元自身も予想できないことであった。そのため、創刊時からしばらくの間は、計画的に再版の刊行を予定して組版を残しておくことはせず、売り切れるたびに版を組み直して刊行するという状態であったようである。
最も典型的な例としては、まず何よりも創刊号(前掲)の場合をあげるべきであろう。
| 図2A 底本 | 図2B 異版 |
|---|
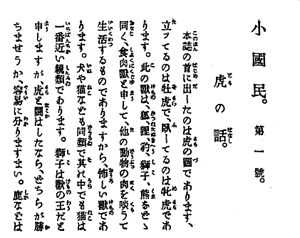 | 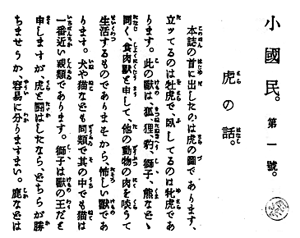 |
創刊10周年を記念した記事「少国民歴史」(「少国民」第10年第2号所収 1898年1月15日付)によると「当時、高橋氏の、此事業を興すや、多くの資金を積みおきて始めたるには非ざりしも、四六時中眠食を忘れて拮据し、且つ、営利一辺の商人根性を離れて事に従ひしかば、忽ち読者を江湖に得、初版二千五百部を売り尽して直に再版せり。」という。このように、当の発行人自体が予想だにしないほどの売れ行きであった。そのため、解版しては新たに版を組み直すという、かなり場当たり的な方法による追加発行を繰り返すのである。本文の組版に着目して、そのありようを考察してみたい。
復刻版の創刊号の表紙には「再版」と表示がある。つまり、再版を底本にして復刻を行ったのである。むろん、復刻にあたっては本来「初版」を底本とすべきだが、手を尽くして探してもどうしても初版を発見することができなかった。そのため、やむをえず「再版」を底本にせざるを得なかったのである。ところが、たいへん興味深いことに、同じ「再版」と表示があっても内容の異なる版が存在している。図1Aは復刻版の底本となった「再版」であり、図1Bはその異版である。ともに表紙には「再版」と明示されているので、一見するとこの2冊はまったく同一のものであるかのように見える。しかし、この2種類の「再版」の誌面を詳しく比較してみると、記事の内容自体は同一でありながら、異なる字体の活字によって本文が組まれているのである。特に仮名の活字に注目すると、例えば「し」「は」「り」「す」などについて字体の違いが顕著である。
これらはおそらく次の手順で刊行されたものと思われる。すなわち、まず、創刊号の初版が刊行されて売り切れた。次に、版を組み直して「再版」が刊行された。その「再版」も売り切れたので、もう一度版を組み直して新たな「再版」が刊行されたのである。してみると、「再版」は初版に次ぐ第2版という意味ではなく、版を新たにして刊行したというほどの意味なのかもしれない。
次の例は、第1年第4号(1889年10月10日付)についてである。
| 図2A 底本 | 図2B 異版 |
|---|
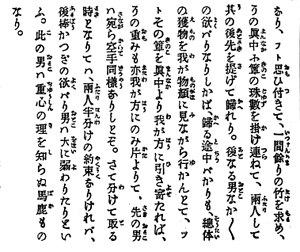 | 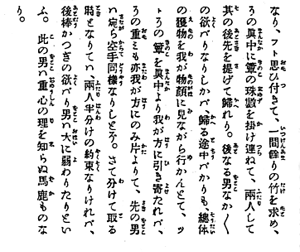 |
図2Aは底本、図2Bは異版であって、本文記事としては第1頁めの下段の部分にあたる。どちらも表紙に「再版」という表記はなく、一見すると「初版」であるかのように思える。しかし、特に仮名に注目すると字体の違いは顕著で、図2Aと図2Bとでは版が違うことが明らかである。字体の違いだけでなく、最終行の「なり」をみると、行までが変わっている。さらに、図2Aと同じ頁の上段には「佐松の中将より初簟の小将まで」の部分について「小将」という誤植がある。これを図2Bでは「少将」に訂正している。したがって、「再版」という表記はなくとも、図2Bは図2Aより後に編集・刊行されと考えるのが順当であろう。つまり、まず、第4号の初版(底本)が刊行されて売り切れた。次に、版を組み直して「再版」(異版)が刊行されたが、その際に「再版」と表示されることはなかったのである。
なお、図1Bと図2Bは大阪国際児童文学館の所蔵資料であり、どちらにも「永田」という押印がある。これはある時期の所蔵者の印鑑であろう。おそらく、同一人が同一経路で入手したものと思われる。図2Bは図2Aより後に編集・刊行されたと推定できるので、図1Bも図1Aより後の時期に刊行されたものと推定するのが妥当であるように思える。
さらに、第2年第14号(1890年7月3日付)の場合は奥付の形式や広告に相違がある。
| 図3A 底本 | 図3B 異版 |
|---|
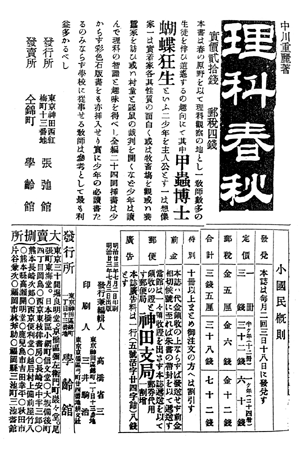 | 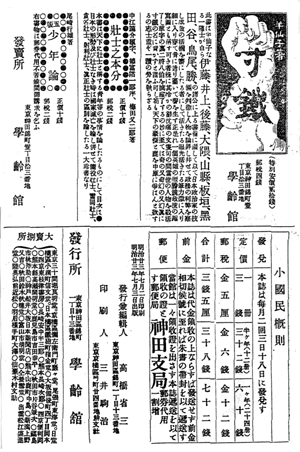 |
図3Aは底本、図3Bは異版である。奥付の日付を見る限りでは、図3Aと図3Bは同一の版でなければならないものの、現実には広告・概則・奥付の記述や形式がまったく異なっている。どちらが先に刊行されたものかは判断しがたいが、前後の号の「概則」の記述内容と形式が同一であることから、復刻にあたっては図3Aの方を底本に採用している。
ところで、「小国民」の再版には表紙に「再版」と明記してあるものが多い。復刻版は「再版」と表示のないものを底本とするのが原則であったが、復刻の作業の過程で多くの「再版」と明示された版を確認することができた。「再版」と明記した場合は、初版の版を解版した後で新たに組版を行い、改めて「再版」として再発行したものと、一応は考えられよう。ただ、これとは別に、初版・再版の区別をしないまま、異なる版または刷りの製品を刊行した場合もあった。同じ「再版」と表示があっても、実際には版が違っている場合もあった。また、本来の「初版」を売り切ってから「再版」を発行するのではなく、両者を同時並行的に販売していた場合があったかもしれない。あるいは、こうした異なるケースが複雑に入り組んでいたのかもしれない。
最後に、「小国民」の広告類には、既刊分を合本して販売するという類いのものを多く目にすることができる。少なくとも初期の頃の号については、在庫を合本して売りさばくという趣旨ではなく、新たに印刷・刊行した再版以降または2刷以降のものを合本して販売したものと考えられる。この合本販売分をめぐる問題については調べがつかなかったことを付け加えておく。
(3)図版について
「小国民」の特徴の一つに、挿画や図版に力を入れていたことがあげられる。
『北隆館五十年を語る』(1940年11月4日 北隆館)によれば、「少(ママ)国民の特色といふべきは挿画である(ママ)少年を楽ますには挿画が何より効果があるが、費用が多くかゝるので中々出来ぬ事である。而るに少(ママ)国民は殆ど制限なく挿入した、(ママ)十冊中に大小八九十を入れた事は珍しくなかつた」という。「写真とか洋画とかは西洋木版を用ひた。これは俗にツヽキボリといつた彫方で山本芳翠といふ人が仏蘭西で学び、明治二十年頃帰朝して日本で創めたもので、刻料は日本木板の数倍であつたが少(ママ)国民はこれを用ひた」という記述もある。
また、「少国民歴史」(前掲)によれば、「始め、少年の雑誌は文章と画と相待たざるべからざるを悟り、極めて挿画を豊にして、文章の意義を助けんことを期し居りしが、発売部数の増すに従ひ、本年(1891年―引用者)五号以下は、三十余版づゝを挿むに至れり。これ等、従来の諸雑誌には絶て無きことなり。而して第七号より、西洋木口版を挿みしが、日を追ひて、其彫刻も精巧になり、漸次世に行はれたり。」と記されている。西洋木口版については、佐久間文吾と精巧館彫刻部が担当したとの記述もある。精巧館とは、フランスで木口木版の彫刻を研究して帰朝した合田清が創設したものである。
こうして「小国民」では、最先端の印刷技術を取り入れながら、これまでの児童雑誌に例のないほど大量の挿画や図版を掲載していたのである。
主筆の石井研堂が如何に挿画や図版に心を砕いていたかを知る手がかりとして、第2年第16号(1890年8月3日付)は好例である。
| 図4A 底本 | 図4B 異版 |
|---|
 |  |
図4Aは底本、図4Bは異版である。活字の種類や活字の組み方は同じであるが、図版が異なっている。平家蟹の図は、底本では左上を向くように配置されている一方、異本では右上を向くように配されている。要するに同じ図版のむきを変えただけである。おそらく解版をしないまま、平家蟹の図版のむきだけを変えたものと思われる。図版を詳細に調べてみても、版面が摩耗したために取り替える必要が生じ、増刷の機会に平家蟹の向きを変えたようには思えない。したがって、技術的な要因から平家蟹の向きが変更されたのではなく、増刷を機会に編集者である石井研堂の強い意思が働いて変更されたと考えるべきである。「版」の違いというより、今日でいう「刷」の違いと認識すべきであろうか。
このように、図柄からみて平家蟹の図版は同一のものを使用しているが、見開いて左側の頁への掲載であるから、レイアウト上のバランスからいえば、明らかに左向きの図版に軍配があがるだろう。ただし、これでは図4Aと図4Bの成立の後先を確定できるほどの強い根拠とまでは言えない。
そこで、図4A・4Bのいずれでもない大阪国際児童文学館所蔵本に注目する。蟹の向きは図4Bと同じである。少しわかりにくいが、図4Bでは7行目の「こと」にあたる活字が不鮮明であるので、この部分を大阪国際児童文学館所蔵本で確認すると全く同じ状態である。つまり、「こと」にあたる字は印刷機の調子が悪くてたまたま1冊分だけが不鮮明になったのではなく、活字が欠損していたか、摩耗していたかのどちらかであろう。活字自体に原因があったため、このときの印刷分の全体が不鮮明になったと考えられる。しかし、図4Aの同じ部分を見ると印刷状態は鮮明で、傷んだ活字は取り替えられたようだ。正常な活字をわざわざ傷んだ活字に取り替えることは考えられないから、おそらく蟹の図版の向きを変える際、傷んだ活字も取り替えておいたとみるべきだろう。
これで図4Aと図4Bの成立の前後関係が確定できる。すなわち、図4Bがまず印刷され、しかるのちに図4Aが印刷されたと考えることができるのである。
次に、第2年第17号(1890年8月18日付)の例である。図5Aは底本、図5Bは異版である。本文の組版は同一であるが、図版の人物の目が異なっている。
| 図5A 底本 | 図5B 異版 |
|---|
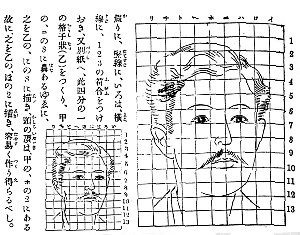 | 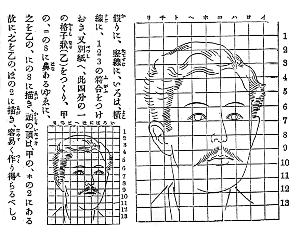 |
当時は写真が高価であったため、書画を安価に拡大または縮小して複製する技術が求められていた。この記事はその方法を紹介したものである。おそらく、最初は図5Bのように白目のまま印刷したものが気に入らず、目の部分に手を加えて図5Aの状態に変更したものであろう。図5Aをよく見ると瞳の部分がいびつであり、いかにも後から手を加えたらしいことが見て取れる。
以上、本文の組版は共通でありながら、図版のみを変更した例を見てきた。これらはいったん解版をしたあと新たに版を組み直したものではない。明らかに、解版せずに保存しておき、複数の回に分けて印刷が行われたものである。ここから次のような推定が成り立つ。すなわち、さまざまな事情から発行する雑誌の総てを一度に印刷することはせず、複数の回に分けて印刷が行われた。その過程で版に手を入れながら印刷を続けていったため、結果として複数の種類の異版ができた。それらが初版・再版、あるいは初刷・2刷として区別されることなく、出荷・販売されていたということである。
解版のあと新たに版を組み直したと思われる例は、初期の頃の「小国民」に集中している。だとすると、初版の印刷が終了した後も解版をせず増刷に備えるようになったのかもしれない。つまり、この雑誌の売れ行きが爆発的に増加していったことから、いずれの時点からか、初版の印刷終了後も解版をしなくなったのではあるまいか。そして、増刷の機会を捉えて、初刷の際に不備であったと思われる図版や傷んだ活字に手を加えていったと考えられるのである。
(4)口絵について
先に、「小国民」の特徴の一つが挿画や図版に力を入れていたことであることを述べた。しかし、何よりも石井研堂が力を注いだことは、多色刷りの口絵についてであろう。
「小国民の挿画」(第5年第24号 1893年12月18日付)と題する記事にも「画工を選み、彫刻師を選み、与に其技倆の十分を尽さしめて、明治の今日に成る挿画の最高程度を後の世に伝へんと欲する」云々という記述がある。「少国民歴史」(前掲)には「画は、初号二号共、尾形月耕氏の揮毫を請ひしが、第三号より小林清親氏に改めたり。」「第九号(1890年2月10日付―引用者)口絵は、彩色摺となせり。少年雑誌にて彩色口絵を挿むこと、之を嚆矢とす。」とある。さらに、その後の推移については、第3年第16号(1891年8月18日付)から「挿画の一部を富岡永洗に托することとなる。」こと、1893年より「小堀鞆音氏が、二十三号以下、専ら本誌のために彩筆を揮はる」こと、1894年の「冬より、前田竹坡尾竹国観二氏小堀氏に従ひて筆を執り、後、絵画部担当主任となる。」ことなどに、大きなスペースが割かれている。
「小国民」の口絵については、木村小舟『少年文学史 明治篇』(前掲)で、次のようにも記されている。
かやうにして「小国民」の挿画は、号を重ねるに連れて、少しづゝ其の数を増し、且緻密の度をも加へたが、遂に創刊後九ケ月目に至つて、其の口絵に、初めて石版数度刷を用ゐて、「牛若丸気質鍛錬の図」を掲げ、誌界稀に見るの一大光彩を露呈し来つた。図は小林清親の筆に成り、赤衣紫袴の小英雄牛若が、鞍馬の奥に木刀を提げて、老樹の幹を睥睨する光景を現し、真に人目を眩すべき見事の出来栄であつた。而もこれは我国に於ける少年雑誌に、初めて試みられしもので、此の意味に於ても、此の一面の多色刷石版画は、記念すべき者と見なければならぬ。
今日では多色刷りの口絵などさほどとも思わないが、当時としては思い切った試みであった。第2年第8号(1890年1月10日付)の「館告」に「彩色石版画附録次号ヨリハ毎号必ス相添ヘ可申ニ付此段広告ス」と予告するほどで、以後は同誌の呼び物となった。確かに、同時期に刊行されていた「少年園」と比較しても、時代の先端を行く突出した試みであった。
また、「十六号に、写真銅版の口絵を挿みたりしが、当時、最新の印刷物として、世に歓迎せられたり。」(「少国民歴史」)とも、伝えられている。実際にはこの記述は誤りで、写真銅版「シャム国皇太子元服の大礼」が掲載されたのは第3年第15号(1891年8月3日付)である。写真銅版(網目版)は小川一真が帰朝して、わが国で初めて発表。「小国民」のこの号へ、雑誌の挿絵・口絵としては最初に採用されたという。当時としては最も先端的な技術が取り入れられたのである。
かくして、「雑誌で儲けた丈は、悉く其雑誌の挿絵や印刷費に掛けて了ふ」(『「小国民」綜覧』)と言われるほどにまでなった。このように力を入れた口絵であるからこそ、もし研堂の意に添わない場合には、いったん印刷・刊行した後でも機会があるごとに改訂を加えていった。そのため、結果として多くの異版が世に出ることになったのである。ただでさえ多色刷の口絵にはコストのかかものであるが、さらに刷り直しや差し替えに要する余分な出費と手数を厭わなかった。研堂がいかに口絵に力を入れていたかが窺えるので、ここでは口絵の異版について取り上げる。
まず、同じ口絵について刷り直しを行ったと思われる場合である。
| 底本 | 異版 |
|---|
 |  |
第2年第13号(1890年6月10日付)の口絵「村上義光錦旗を奪ふ」(小林清親・画)には、底本のように発色状態の良い版と極めて発色の悪い異版の存在を確認することができる。この口絵は南朝方の武将・村上義光が北朝方に錦の御旗を奪われたことを知って「これ親王の賊を討つ旗なり。奴輩いづくんぞ之を奪ふことを得ん。」と激怒。「其僕をとらへて、二三丈の外に投げ」て奪われた錦旗を奪い返す場面を描いたものである。であるから、錦の御旗はこの場面の道具立てとしてきわめて重要であり、錦の御旗が「錦」でなければ話にならない。ところが、経年変化による退色のあることを考慮しても、明らかに発色が悪い異版が存在する。口絵の図柄そのものは殆ど同一である。細かな相違としては、異版にある清親の落款が底本では欠落しているぐらいである。版の違いというより刷の違いと認識すべきだろうか。この場合は、おそらく、印刷の仕上がりが悪いため口絵を刷り直したものと考えられる。
次に、ほぼ同一の構図の口絵、または同じ口絵に手を加えたと思われる場合である。
第2年第16号(1890年8月3日付)の口絵は「神功皇后三韓御征伐の図」である。おそらく、画家は小林清親であろう。
| 図6A 底本 | 図6B 異版 |
|---|
 |  |
図柄はいわゆる神功皇后の三韓征伐を描いたもの。図6Aは底本、図6Bは異版である。神功皇后の武威に恐れをなした新羅王は「惶れあわてゝ為す所を知らず、面縛して来り降る」ことになる。高麗百済の二国も「風を望んで帰化」して、「三韓悉く服す」という。口絵の場面は「是より三韓我が西蕃と称し、永く絹帛を貢して敢て渝ることなし」と、三韓の使者が貢ぎ物を捧げている場面である。太刀を付けた皇后が立つ前に三韓の使者が謹んで臣従の意を表わす構図は共通している。しかし、図6Bの皇后は質素な無地の着物を着用している。それにひきかえ、使者は豪華な着物を着用し、貢ぎ物の反物もまた豪華である。これでは皇后の方が使者より見劣りしてしまう。一方、図6Aの皇后は白地ではあるが模様の入った豪華な着物を着用しており、決して使者に見劣りするようなことはない。つまり、図6Bが貢ぎ物をささげる使者の豪華な着物と比較して皇后の着物が質素であることを気にしたため、図6Aのように変更したのであろう。着物の柄を除いては同じ輪郭であることから、あるいは同じ原画に手を加え、刷りの工程を1工程分増やすことにしただけかもしれない。
さらに、構図は似ているが別の絵に差し替えた場合である。
| 図7A 底本 | 図7B 異版 |
|---|
 |  |
第2年第21号(1890年10月18日付)の口絵は「暁斎翁幼児習画の図」である。異版には「清親」の署名、底本には「政直」の署名がある。「政直」は不祥だが、清親の弟子であろうか。
子ども時代の川鍋暁斎が、増水した神田川の川辺で生首を見つけ、絵の修行のため生首を写生しようと家に持ち帰る。しかし、父から「家にて之を写さば、官の咎めもありぬべし、故に其拾ひし所に於て、写すに如くはなし」と諭されて、やむを得ず生首を元の川辺にもどし、写生をしている場面である。例によって図7Aは底本、図7Bは異版である。ほぼ同じ構図だが、図7Bでは暁斎の後ろで驚いている武士の表情や身振りに難がある。図7Aはこれを改めたほか、その他の通行人や子どもの着物に手が加えられた。
右斜め上の絵は、暁斎が生首を写生している場所の背景を配したものである。増水した神田川と水道橋と思われる橋のようすが描かれているが、図7Aは図7Bと比べてかなり省略がなされている。この場面の背景である増水する川の情景を詳しく写実的に描きすぎると、かえって焦点を分散させてしまう。そのため、図7Aでは川の情景を省略した絵柄に差し替えたと考えるのが順当だろう。
第2年第24号(1890年12月3日付)の口絵は「風船乗実况図」(小林清親・画)である。
| 図8A 底本(部分) | 図8B 異版(部分) |
|---|
 |  |
図柄は上野公園で興行されて評判をとったスペンサーの気球乗りを描いたもの。後年、研堂はこの興行のことについて、『増補改訂明治事物起原』下巻(1944年12月28日 春陽堂)に取り上げて、「明治二十三年、英人スペンサー氏、横浜にて風船乗を興行し、十一月十二日、東京に上りて天覧に供し、同二十四日、上野博物館内の広場にて興行し、縦覧せしむ、索つきのまゝよく上昇の目的を達せり。入場料は、上等一円、中等五十銭、下等二十銭、小児は半額の定めなりし。」と記している。また、本文記事「風船乗実見の記」には「今回、東京上野公園にて興行する、模様を、小国民諸氏に詳報せんかため、記者は、画工と倶に、態々上野にむけ出発せり。」とある。記者とは研堂、画工とは清親のことに違いあるまい。つまり、好奇心旺盛な研堂は自らスペンサーの興行を見物に行ったのであり、『明治事物起原』中の記事はそのときの体験をもとに書いたものということになる。そういえば「索つきのまゝよく上昇の目的を達せり」というくだりは、いかにも実見した者ならではの感想を思わせる。今日ならカメラマンを伴って取材に出かけたことであろうが、技術的な問題から報道写真の替わりに清親に口絵を依頼したのである。雑誌の発行の日付が興行の行われた日からわずか9日めであることも、当時としては速報性のある報道記事であった。研堂の編集にかける意気込みと凝りようがわかる。
後方のレンガ造りの建物はおそらく上野の博物館であろう。本文記事中に「博物館構内、館前中央の広場にて興行す。」とあるからである。図8Aは底本、図8Bは異版である。図8Aには清親の署名があり、図8Bと比べると博物館の窓や樹木がより写実的に描かれている。報道写真の代替として口絵を利用したのであり、タイトルにも《実况図》とある。《小国民諸氏に詳報せんかため》という記述からしても、図8Bを8Aに取り替えたとみたい。
第2年第25号(1890年12月18日付)の口絵は「東京歳の市の真景」で、これも小林清親の作であろう。本文記事中に「芝の愛宕下に、或は神田明神下に、其他各町各所、両側一寸の地を残さず、露店幾万、燈焔天を焦がして火事かと疑はれ、四民狂奔して戦争かと恠まれ、西に往くもの、東に往くもの、匆々足を早めて来往織るが如きは、歳の市の概景なり。」と、その賑わいぶりが活写されている。
| 図9A 底本(部分) | 図9B 異版(部分) |
|---|
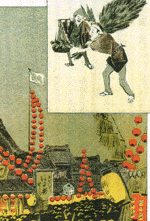 |  |
図9Aは底本、図9Bは異版である。両図は甲乙いずれともつけがたいが、右上の2人の人物は雑踏の中の物売りを描いたものである。本文記事によると、一人は雪掃(ゆきはき)売りで、「東京、年々雪寸に満たざるに、尚雪掃を売るものあるは、昔の江戸の大雪ありしを證するに足る」とある。図9Aでは雪掃が図9Bよりリアルに描かれて、本文に対応している。「こゝを以て、佇立して細密の観察を遂げんとするは、容易の事にあらずと、言訳を申しつゝ」云々と《細密》さを強調する本文との対応から見ても、図9Bを図9Aに変更したものと判断したい。
また、この号については「二ノ宮金次郎伝」に挿入された挿絵(一色刷り・無題)にも異版があるが、ここではその事実だけを報告しておく。
最後に、口絵を全く別の絵柄のものに差し替えた場合である。
第2年第19号(1890年9月18日付)の口絵は「松平信綱剛胆の図」(小林清親・画)である。
| 図10A 底本 | 図10B 異版 |
|---|
 |  |
図10Aは底本である。夜中のただならぬ物音に驚いた将軍・徳川秀忠が寝間着姿のまま大刀をひっさげている。身振りからして松平信綱を厳しく叱責している。11歳の信綱は若君(家光)から奥御殿の屋根の上の雀の巣から雀の雛を獲ってくるよう命じられたが、誤って屋根から転落する。だが、将軍から問いつめられても信綱は「臣雀児を見て之を愛し、ひそかに来り捕らふるなり」「臣自ら之を為したることにて、他人の言付け等にあらず」と平伏するばかり。もとより、若君をかばってのことである。しかし、事情をさとった源崇(げんすう)夫人が気の毒に思って信綱を取りなし、秀忠も信綱の剛胆に感心して「彼の児、今にして斯の如くなれば、成長の後は、必ず良き輔臣たらん」と罪を不問にする。中央右よりには、この場面で重要な役割を果たす源崇夫人の姿が、大きく描かれている。緊迫感にあふれ、本文の内容にそって過不足なく描いたみごとな図柄だといえよう。
図10Bでは、信綱は庭に平伏している。一方、夜中の突発的な出来事にもかかわらず、将軍はきちんと袴を着けた姿で脇差しのみを帯び、殿上に立っている。秀忠将軍に驚きや動揺の様子はすでに見えない。源崇夫人の姿はなく、代わりに殿居役と思われる2名の武士が控えている。事件自体はすでに収束し、将軍の裁きを待つ様子を描いたものであろう。どちらの絵も清親の筆になるとはいえ、異版には緊迫感があまり感じられない。
絵画としてはいずれも遜色ない出来であるが、ここで重要なことは、本文記事との整合性である。本文中には殿居の武士に関する記述は全く存在せず、源崇夫人が取りなし役として重要な役割を果たしている。「将軍は驚き起き、刀を提げて出で来り」云々という表現にも合致しない。したがって、この場面の口絵としては明らかに図10Aの方がふさわしい。
第2年第23号(1890年11月18日付)の口絵は「木村重成の図」(小林清親・画)である。
| 図11A 底本 | 図11B 異版 |
|---|
 |  |
この場面は大坂城冬の陣で、和議の文書を取り交わすため徳川家康と大坂方の武将・木村重成が対面するところを描いたものである。重成は家康の血判が鮮明でないことを指摘し、改めて血判を押すことを要求。家康とその周辺に居並ぶ徳川方の諸将を少しも恐れず、堂々と渡り合う重成の勇気を主題とする口絵である。本文記事中では「重成の如きは、他に使して君命を辱かしめざる良臣といふべく、其父を辱かしめざる孝子といふべし。此の如き美徳は、沈厚慎密の人の能くする所にして、軽佻急躁の人の能くせざる所なり。」と誉め称えられている。
この会見の場面を描く図11A(底本)と図11B(異版)では、家康と重成の位置関係が逆になっている。これは、この場面の視点の問題である。すなわち、この場面が重成の側から描かれているのか、家康の側から描かれているのかの違いのあらわれである。本文との整合性からすると、図11Aがこの場面にふさわしい。なぜなら、本文記事中で重成が登場する場面は「美々しき装束にて馬にまたがり、茶臼山の営(家康の本陣)に至りしに」で始まり、「遂に血判づきの誓書を取り、拝謝して還れり。」で終わっているからである。家康の陣に敵方の使者(重成)を迎えるのだから、この場面は家康の側から描かれるべきなのである。重成が背後に居並ぶ徳川方の諸将を恐れず、「徳川の臣、土井利勝等、之をしりぞけて、下座に着かしめんとせしも、重成顧みずして進み出で、秀頼の命をのべ、然る後退きて首を地につけ、誓書の出るを待てり」と、家康と堂々と渡り合うという主題からも、図11Aがふさわしい。図11Bの構図では背後で重成を威嚇する徳川方の諸将を描きようがないからである。
| 図12 底本 | 図12B 異版 |
|---|
 |  |
そのほか、第2年第15号(1890年7月18日付)の口絵「柴田勝家甕ヲ破ル図」のように、一色刷の口絵を多色刷に更えたと思われる例がある。図12Aは底本で多色刷、図12Bは異版で一色刷である。この図柄は敵に水を絶たれた柴田勝家が、逆に城中に貯えた水を捨てることによって味方の奮起を促す故事を描いたもの。図12Bの左後方に見える2人の家来の描き方がおおげさすぎて、悲壮な決意あふれるこの場面の緊迫感にそぐわない。よって、図12Bの口絵を図12Aに取り替えたと判断したい。
以上、詳解してきたとおり、口絵としてはいずれも底本の方が優れていることは明らかである。ただ、異版の成立の事情は不明。清親があらかじめ2枚の絵を仕上げて研堂に渡しておいたものか、最初の絵が研堂の気に入らなかったため描き直しを依頼したものかまではわからない。ここで言えることは、研堂が手数と費用を惜しまず、口絵を重視したことの反映だということである。また、画家が口絵を手がける時には、既に本文が脱稿されているか、または構想が固まっていて、内容を把握できるとは限らない。本文との相違が清親に責任ありとは必ずしも言えないし、それを気にしていたのはむしろ清親の方かもしれない。少なくとも、研堂が口絵と本文の相違を気にしていたことだけは明らかであろう。
(5)終わりに
本稿では「小国民」の異版が多く存在することを明らかにしてきた。多くの異版の存在は、石井研堂が「小国民」誌の編集にあたって挿画や口絵に非常な気配りをし、いかに手数と費用を惜しまず力を尽くしたかということを跡づけている。この時代の児童雑誌は、「少年園」に山縣悌三郎があり、「小国民」に石井研堂があるというように、強固な理念をもった主宰者があった。「少年園」の場合は編集者が経営者をも兼ねていたが、「小国民」の場合は経営者である高橋省三が雑誌の内容に口出しすることは一切なかったという。『北隆館五十年を語る』(前掲)にも「高橋氏は氏(研堂のこと―引用者)を聘して全くこれを委任し、記事に就ては少しも干渉することなく唯紙数を増加するとか、挿画を善くするとか、附録を付けるとか、万事善くする方面に就てのみ相談するばかりで資金損益等の事は其耳にも入れなかつた」とある。経営者が研堂に総てを任せたからこそ、研堂は余分な経費のかかることを殆ど度外視して、自らの満足がいくまで挿画・図版や口絵に手を入れることができたのである。このように出版社の営業や資本の蓄積よりも満足のいく雑誌づくりを優先したことは、研堂の生真面目ぶりのあらわれであるといえよう。反面、大資本を背景にした強力な競争誌「幼年雑誌」が博文館から創刊(1891年1月1日付)され、ひとたび経営がつまずくや発行権の譲渡をせざるをえないところまで追い詰められていった原因の一つとなったことも否定できない。
ところで、本稿の脱稿直前になって鳥越信『児童雑誌「小国民」解題と細目』(2001年1月15日 風間書房)が上梓された。しかし、これは以前に鳥越がわたしを含む複数の研究者と共著で「大阪国際児童文学館紀要」に連載した旧稿にやや手を加え、これを鳥越が自らの単著として刊行したにすぎない。手を加えたといっても、復刻版の対象となった時代については、復刻版を利用して旧稿の欠落を補充したことや、「あとがき」で大阪国際児童文学館の所蔵本と復刻版の相違を指摘したことが中心である。「全面的な増補・改訂の手直しを加えた」とか、「今回はすべて私個人の責任で、第一歩から改めて作りあげることとした」と大書するなら、復刻版や乱丁・落丁・破損本を含む一揃いだけの資料を底本にして事を済ますべきではあるまい。改めて異版を含む複数の種類の原資料にあたり再調査することあってしかるべきであろう。
雑誌の総目次や年表、復刻版などが整備され、日本児童文学をめぐる研究環境は従来に比べて格段に向上している。しかし、一揃いの原本さえ手元にあれば総目次(細目)や復刻版を作成できるというものではない。可能な限り複数の原資料にあたり、それらを比較検討することを通して、初めて学問的に意味のある業績を成し遂げることができる。とりわけ、明治期の出版物については、そういうことがより慎重になされねばならない。例えば、明治期の単行本について、重版の奥付に記された初版年月日が実際の初版年月日とずれていることの多いことは、専門家の間の常識として従来からよく知られている。本稿を通じてわかるように、奥付などから初版であることが明らかであると思われる場合においてさえ、そのことが必ずしも真実ではない場合もある。また、口絵にしても本文記事と同時期に印刷されたとは限らない。口絵と本文記事を異なる業者がそれぞれ分担して印刷していた可能性すらないとは言い切れない。印刷時期の違う口絵とその異版、本文記事とその異版がさまざまな組み合わせで製本され、さまざまな流通経路を経て末端の読者の手に渡っていったとすると、事態はきわめて複雑である。少なくとも、今日でいう初版・再版、初刷・2刷というような概念でこの時期の「小国民」誌の異版の問題を整理しようとすることは、適切な方法とは言えないだろう。
書誌学的研究の奥は深く、われわれ研究者が解明してきた事実はまだごく一部にしかすぎないのである。
【附記】
本稿は日本児童文学学会第39回研究大会(2000年10月14日 愛知県立大学)における口頭発表がもとになっている。執筆にあたっては、発表内容に大幅な加筆・修正を加えた。なお、研究資料の収集については、児童文化研究家の上笙一郎氏と不二出版の山本有紀乃氏のお世話になった。