山猫軒の料理メニュー 《エッセイ》
雑誌の時代
―翻訳ものから見た大衆的雑誌と芸術的雑誌のあいだ―
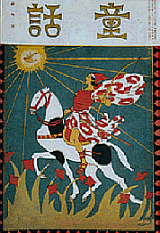 大正期は雑誌の時代である。1918年7月に「赤い鳥」が創刊されたことをきっかけに、芸術的児童文学の雑誌の創刊が続いた。翌年の4月には「おとぎの世界」、7月には「こども雑誌」、11月には「金の船」(のち「金の星」)、さらにその翌年の4月には「童話」などといった状況である。一方、大衆的児童文学の雑誌には「少年世界」「日本少年」「少年倶楽部」「少女倶楽部」「少年少女譚海」などがあった。
大正期は雑誌の時代である。1918年7月に「赤い鳥」が創刊されたことをきっかけに、芸術的児童文学の雑誌の創刊が続いた。翌年の4月には「おとぎの世界」、7月には「こども雑誌」、11月には「金の船」(のち「金の星」)、さらにその翌年の4月には「童話」などといった状況である。一方、大衆的児童文学の雑誌には「少年世界」「日本少年」「少年倶楽部」「少女倶楽部」「少年少女譚海」などがあった。
一般に日本の児童文学は芸術的児童文学と大衆的児童文学が独自の道を歩む複線型の構造をしているといわれる。そして、ある児童文学作品が芸術的児童文学または大衆的児童文学のいずれに分類されるかは、発表誌の違いに求められることが多い。だが発表誌による区分がどれほど有効性を持っているのかということに、わたしは懐疑的である。
たとえば「少年少女譚海」は老舗の出版社・博文館が後発の「日本少年」(実業之日本社)や「少年倶楽部」(大日本雄弁会講談社)に児童雑誌市場を席巻されている状況に対抗し、1920年1月に創刊した雑誌である。誌面はエンターテイメント性を前面に打ち出した構成で、歴史もの・講談もの・英雄豪傑伝などを掲載した。「日本少年」や「少年倶楽部」より、さらに《低俗》な雑誌とされている。
しかし、この雑誌に森下雨村は「ヂツケンス物語」と題して「孤児オリバー」(1921年4月〜7月号)と「少女ネル」(同年8月〜12月号)を連載している。当時、雨村は博文館で探偵小説を看板にした「新青年」(1920年1月創刊)の編集長をつとめていた。一般には大衆的児童文学の作家と認識され、他社の児童雑誌も含めて冒険小説や探偵小説などを盛んに発表している。その一方で、自社の雑誌にディケンズの訳を掲載していたのである。雨村とは逆に、西条八十は一般には芸術的児童文学の作家と認識されているが、「童話」の1923年9月号に寄稿した「昆虫博士」はドイルの探偵小説《甲虫採集家》である。また、同じ雑誌に「眼に見えない男」(1924年5月〜25年4月号・連載中断)の連載も行っている。これはウェルズの《透明人間》である。こうした例は、大衆的児童文学の作家と芸術的児童文学の作家、大衆的雑誌と芸術的雑誌の間にみられる、みごとなまでの逆転現象である。
もともと、「少年少女譚海」は博文館の経営の立て直しを図るため、エンターテイメント性の高い作品から芸術的児童文学に分類されるような作品まで、幅広い分野の作品を掲載する編集方針をとった。創刊号からしばらくは、鹿島鳴秋がスウィフトの《ガリバー旅行記》を連載。すなわち「小人島奇譚」(1920年1月〜6月号)と「大人国奇譚」(1920年7月〜21年3月号)である。奇しくもこの年の「赤い鳥」には、野上豊一郎が「馬の国」(1920年5〜8月号)を連載していて、大衆的児童雑誌と芸術的児童雑誌が競い合うように「ガリバー旅行記」を掲載したのである。
同じ博文館から出ていた「少年世界」でも、大槻憲二の訳で「ドーリットル博士の航海」(1925年1月号〜12月号?)を連載した。いうまでもなくロフティングの《ドリトル先生》ものの翻訳である。連載の最終号は未確認だが、おそらくこの年の12月号であろうと思われる。しかも、ほぼ同時期のこの雑誌にはコロディーの《ピノキオ》が並行して連載されているのだ。水野葉舟の「マリオネットの冒険」(1925年1月号〜8月号?)がそれである。この翻訳についても連載の最終回は未確認だが、おそらくこの年の8月号までの連載であると思われる。ここで少し、わが国における《ピノキオ》の翻訳の歴史を見てみよう。
わが国で最初にピノキオが紹介されたのは西村アヤ(のち石田姓)による『ピノチヨ』だとされている。出版は1920年5月のことで、当時、著者はまだ小学校5年生であった。1918年の夏のこと、アヤの父でのちに文化学院を創設することになる西村伊作が、友人の佐藤春夫から《ピノキオ》の英訳本を借りてきた。これをもとにして、夕食後などに訳しながら自分の子どもたちにストーリーを話してきかせた。それを思い出した長女のアヤに、「ピノチヨのお話を書いたらどうだ、おとぎ話の本を作ツて見よ」と伊作が奨めたことがきっかけで、この本が誕生したのである。そして、「金の船」の版元であったキンノツノ社(現・金の星社)を経営していた友人・斎藤佐次郎に依頼して出版の運びになったものだという。
その一方で、佐藤春夫は「赤い鳥」に「いたづら人形の冒険」と題して《ピノキオ》の連載をおこなっている。1920年2月号から連載を開始し、9月号で中断。友人に英訳本を貸した佐藤が小学生の女の子に出し抜かれたかっこうである。また、武田雪夫は「ピノツチヨ」というタイトルで「童話」に連載した。1924年2月号から連載が開始され、同年6月号で中断している。
このように、芸術的児童雑誌と大衆的児童雑誌の枠組みを超えて、《ピノキオ》の翻訳・紹介が行われたのである。それにしても、こうした現象は、何も他社にシェアを奪われていた博文館の雑誌が、たまたま苦し紛れに「何でもあり」の編集方針に走ったからではない。その証拠に、「日本少年」の1921年9月号は「世界童話号」と銘うたれている。翻訳・再話者の名前はないが、「ジヤツクと豆の木(英国)」「鉛の兵隊さん(デンマルク)」「五人兄弟(支那)」「長靴穿いた猫(フランス)」などと並ぶタイトルをみると、これらが「赤い鳥」あたりの目次に並んでいても何ら不思議はない。
もともと、大衆的児童文学と芸術的児童文学の間に、画然とした区分があるわけではない。たとえばスティーブンスンの《宝島》あたりは、どちらに分類されるべきなのだろう。相馬泰三の訳で「童話」に掲載(1922年1月〜12月号)されているから芸術的児童文学である、というように単純な割り切りかたができるものでもない。森下雨村による《オリバー・ツイスト》の訳についても、ある孤児の波瀾万丈の物語という視点でいえば、大衆的雑誌に掲載されても少しも不思議はないといえるかもしれない。そもそも、児童文学を大衆的児童文学と芸術的児童文学に大別することができるようになったのは、「赤い鳥」創刊以降に発生した現象である。初めから二つの系統の児童文学が存在していたわけではない。
日本の児童文学の構造は複線型だというのは、互いに交わることなく独自に展開していくものだという意味だろう。しかし、そういう認識はあまりにも大雑把な理解でありすぎるようだ。大衆的児童文学と芸術的児童文学の間には、もっと複雑でダイナミックな関係性があることを認識すべきではないだろうか。
【『図説 子どもの本・翻訳の歩み事典』 柏書房 2002.4.30. 掲載】
|