|
山猫軒の料理メニュー 《エッセイ》
『1928年版 水口』
―巽聖歌の未刊行自筆童謡集について―
巽聖歌が最初に単著として出した童謡集は『雪と驢馬』である。発行所はアルス、1931年12月18日付の刊行。冒頭に師の北原白秋の「序」を掲げ、満を持しての上梓である。初期の童謡の集大成であり、巽の詩業に区切りをつける記念碑的な出版であった。
この第一童謡集の刊行に先立ち、巽自身の手によって複数の自筆童謡集が製作されている。いずれも原稿用紙を二つ折りにして簡単に袋綴じにしただけのもの。特に出版のあてがあっての製作ではない。自分の詩業をまとめておきたいという意識から、このような試みがなされたのであろう。一連の自筆童謡集は巽の生前には未刊行であったものの、巽の手許で大切に保管されてきた。その内容については没後刊行の『巽聖歌作品集』上・下(1977年4月25日 其刊行会)に収載されている。
だが、『巽聖歌作品集』には、なぜか『1928年版 水口』と題された自筆童謡集だけが収載されておらず、一般には存在すら知られていなかった。しかし、この自筆童謡集は次に述べる製作の時期からみて、一連の自筆童謡集の最後を飾っている。この時点までにおける童謡創作活動の集大成として編まれたものであり、新たな出発点となった意味は大きい。
『1928年版 水口』は、四〇〇字詰原稿用紙二つ折り、おもて・うら表紙をあわせ全19枚を袋とじにしたもの。おもて表紙中央に「1928年版」「水口」のタイトルがあり、タイトル下に「巽聖歌」の署名。うら表紙は白紙のままである。おもて表紙には「1928・3・10」の日付のある作品「川窪」の原稿、うら表紙には「1928・3・29」の日付のある作品「街へ行く子」の原稿を、それぞれ裏返しにして転用。どちらの作品も『雲雀』に収録されたものである。序文・目次の類いは全く存在しない。 また、自筆童謡中の一篇「雲雀」は5月の創作であることがわかっている。
1928年といえば、前年から巽は久留米市の日本キリスト教教会で米人牧師の助手兼日本語教師をしている。のちに与田凖一が「九州では君に異状な生活の挫折があつた。精神の飢餓があつた。君は教会の屋根裏に巣をつくり、神の子となつて、そして、牧師の、ヒステリーの細君に三銭の沢庵を買ひにやらされた。わづかに日曜学校と、外人の日本語教師としての報酬が、ガスと、鍋と、きゆすの把手を動かしたのだ」(「チチノキ」VOL.5 NO.1 1932年2月29日)と述べている。この時代は、また、創作活動においても苦難の時代であった。平野直は「巽はその頃、苦悩のどんぞこだつた。泣きながら童謡を作つてゐた。作れないと云つては泣き、作れたと云つては泣いた」(「チチノキ」前掲)と回想する。一連の自筆童謡集の時代こそ、巽にとっては師の白秋から「相互模倣が幾分この頃は目立つて来たやうである。もつと内容の上にも形式の上にも創意を要する。もつと苦しんでもらひたく思ふ」(「赤い鳥」1927年5月号)と批判を受ける創作上の転機となった時期であった。やがてこの年の8月には白秋のすすめで上京してアルス社に入社することになり、苦難の時代は終わりを告げた。
これらの事実を総合して、『1928年版 水口』が久留米時代の終わり頃、上京直前に纏められたと考えるならば、めぐまれない生活の中で童謡の創作をもって世に出ようとした決意が込められているはずである。あるいは、製作の時期が上京直後にまでずれ込むとすれば、念願の上京をはたして童謡の世界に身を置くことのできた興奮の中で纏められたということになる。
貴重な資料ではあるが、内容については紙数の関係から表題作の童謡「水口」についてのみ取り上げざるを得ない。
まず、句読点である。もともと、初出誌の「赤い鳥」では句点がつけられていた。次に手書き童謡集の1927年版『童謡集 水口』ではこれを削除。さらに『1928年版 水口』と『雪と驢馬』では復活している。
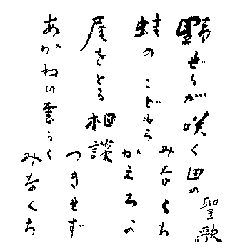 言うまでもなく、句読点の有無は童謡のリズムと密接な関連がある。巽自身は創作時のころを回想して、「水口」で到達した境地について『雪と驢馬』の「追記」で「『水口』の四四四調、『野芹』の三三三・四四四調は何れの世にか若しもあつたとしても、あの場合、私にとつては新発見の沃野であり、私の内的生活も、環境もあれ以外には表現のしようがなかつたのである」と述べている。すなわち、この《四四四》調のリズムこそが、「水口」において到達した技法上の達成点であった。そして、各連の最後に句点を打つという行為は、このリズムをより明示的に浮かび上がらせる効果をあげるであろう。ちなみに、晩年の色紙(1981年、故郷の日詰で詩碑が建立された際に配付)には句点がなく、字配りからすれば《八四》調に近い。字配りは必ずしも確実な証拠ではないが、《四四四》調のリズムで明確な区切りをつけようとする意思が薄れていると考えられる。自由律の時代をくぐり抜けた上での心境の変化の反映とは言えないだろうか。
言うまでもなく、句読点の有無は童謡のリズムと密接な関連がある。巽自身は創作時のころを回想して、「水口」で到達した境地について『雪と驢馬』の「追記」で「『水口』の四四四調、『野芹』の三三三・四四四調は何れの世にか若しもあつたとしても、あの場合、私にとつては新発見の沃野であり、私の内的生活も、環境もあれ以外には表現のしようがなかつたのである」と述べている。すなわち、この《四四四》調のリズムこそが、「水口」において到達した技法上の達成点であった。そして、各連の最後に句点を打つという行為は、このリズムをより明示的に浮かび上がらせる効果をあげるであろう。ちなみに、晩年の色紙(1981年、故郷の日詰で詩碑が建立された際に配付)には句点がなく、字配りからすれば《八四》調に近い。字配りは必ずしも確実な証拠ではないが、《四四四》調のリズムで明確な区切りをつけようとする意思が薄れていると考えられる。自由律の時代をくぐり抜けた上での心境の変化の反映とは言えないだろうか。
次に、童謡集における配列の順序である。1927年版『童謡集 水口』においては、童謡集の末尾に配されている。この自筆童謡集はこれまでの自己の創作活動の総括として纏められ、「白秋先生へ捧ぐ」という冒頭の献辞がそうした意識のあったことを示している。そういう性格の自筆童謡集の末尾に、自らの創作活動の達成点として「水口」を配したと考えることができる。
一方、『1928年版 水口』では、童謡集の冒頭に配されることとなった。『雪と驢馬』においても同様である。すなわち、巽の詩業の到達点としてよりも、新たな出発点として位置付けられていたと考えられるのではないか。このことは、『雪と驢馬』の刊行をもって己の詩業の到達点とせず、「私はこの童謡集を送り出して第四の転身に向はう。新しいカナンの沃野を望むべく」と『雪と驢馬』の「追記」に自ら記していることを想起させるであろう。
谷悦子は「巽聖歌の童謡について―自筆童謡集『茱萸』を中心に―」(「児童文学研究」第10号1979年9月15日 日本児童文学学会)で、「水口」において師の白秋から激賞された《四四四》調が他の投稿家によって模倣されるようになり、師の批判を受けるに至った事実を指摘する。そして、巽は苦悩の時期を経て「風」に見られる《躍動性》と《七五》調を生み出したと論じている。内容(素材)において、風は《動的》であり《躍動性》のある童謡であることは、谷論文の指摘するとおりであろう。しかし、「風」をして「七五調とみなすことができる」(谷論文)と概括するには無理があるように思う。三音・四音・八音・九音といった例外が多すぎるからである。ただ、それにしても七音と五音の多用は紛れもない事実であり、明らかに《四四四》調に代表される過去のリズムと一線を画する作品であったことには違いない。「水口」から出発し、ようやく「風」に至って新しい境地を切り開いたという自信を得た。師の白秋の批判を克服できたのである。もはや、「水口」の手法(《四四四》調)に拘泥する必要はない。そういう境地が巽をして思い出深い出世作である「水口」を冒頭に配せしめたのであろう。
『1928年版 水口』こそ、実生活上・創作上の行き詰まりを克服し、新たな出発点となった記念すべき自筆童謡集であったことがわかる。
【「日本児童文学学会関西例会発表要旨」 第97回 2000.4.22. 掲載】
|